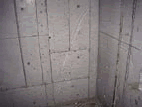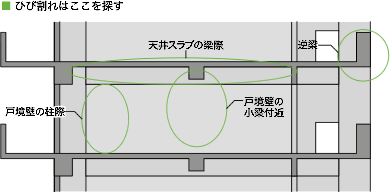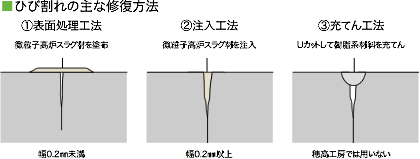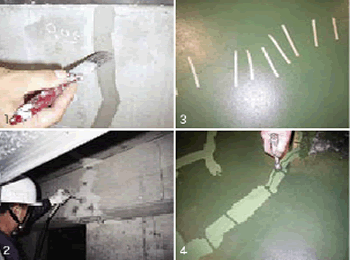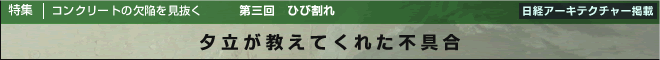
|
| ひび割れを発見するには、型枠を外したすぐ後がよい。穂高工房に協 力してコンクリートの修復に取り組むサイトー工業の斎藤優代表は こう語る。ひび割れが生じやすい個所や、ひび割れの原因が見過ごさ れている個所など、現場で目を光らせる点を解説する。 | |||||||||||
 |
|||||||||||
|
建築に携わる技術屋は、「コンクリートにひび割れはつきもの」と言
う。しかし、マンションを買った一般の人にとって、ひび割れは欠陥マ
ンションの代名詞になっている。ひび割れや漏水の修復屋である筆者
は、そのギャップを痛感している。その顕著な例がひび割れの幅だ。つ
くり手の側では、幅が0.3mm以下のひび割れについては補修が必要ない
と考えている。だが、現実には一見微細なひび割れでもトラブルに発展
する可能性がある。 下の写真は、躯体修復をしている現場で夕立の次の日に発見したひび割れである。 スラブの壁際で見つけたこのひび割れは、幅を実測してみ ると0.15mm以下であった。防水工事をする前の屋上スラブの上に溜った 夕立の水が染み出たことで明らかになった。注意してみると、同じよう なひび割れはほかの階でも発生していた。 このようなひび割れは、コンクリートの中性化や鉄筋の腐食を促す 可能性がある。また万一、上階で水を漏らした時、下階で漏水を起こす 原因となり、深刻なトラブルに発展する可能性がある。 問題になりやすい小さなひび割れの例として、アウトフレームの逆梁 に生じたひび割れがある。干した洗濯物や布団の上に、バルコニーの天 井から水滴がポトリ、ポトリと落ちてくる漏水だ。台風の翌日など、も う雨はあがっているのに水が漏り続ける。しかも、水が垂れてくる天井 面を見てもひび割れは見当たらないし、上階のバルコニー床の防水を調 べても異常はない。つくり手にとっては頭が痛い問題だ。 |
|||||||||||
|
筆者は、原因と思われるひび割れを、コンクリート修復工事をやっているときに発見した。
バルコニーの 逆梁の上端と側面に連続するひび割れを発見したのである。おそらく、
タイルをはった面にもひび割れは発生していて、十分な補修をせずにタイルを施していたのであろう。
仕上げ面のどこかから水が浸入し、ひび割れに到達。水は、しばらくすき間に残っていて、
雨が上がった後も漏り続けたのである。このように、わずかなひび割れであっても大きな問題に
発展する可能性がある。 筆者は、すべてのひび割れに何らかの修復が必要だと感じている。幅 が0.1mmか0.8mmかは関係ない。理由は、漏水を起こすことに加えて、 ひび割れ部分から空気と水分が侵入し、鉄筋の腐食を起こすと考えるか らだ。コンクリートの表面からの中性化を心配するのなら、ひび割れ表 面からの中性化と鉄筋の腐食が進むことも心配すべきではないだろうか。 いかなるひび割れも空気の流れを止めなければならない。 ある大手のマンションデベロッパーは、コンクリート躯体の不具合 修復マニュアルの中で、「0.2mm以上のひび割れには微粒子高炉スラグ材 を注入する。0.2mm未満のひび割れには微粒子高炉スラグ材を塗布する」 と規定している。こうすれば、すべてのひび割れに対処できる。 |
|
||||||||||
設計者や監理者が躯体を見る設計者や監理者が躯体を見るコンクリート打設後の躯体外観を、 構造設計者や監理者がチェックしないことにも疑問を感じる。彼らが 配筋検査で現場を訪れた時、下の階にはコンクリートがむき出しになった 躯体があるにもかかわらず、素通りしてしまう。当然ながら、その躯体に ひび割れが生じていることを知らない。筆者があるマンションデベロッパーの依頼で、脱型直後の躯体外観をチェックした時、 そのデベロッパーの品質担当部門の強い要請で構造設計者(構造監理者でもある)が現場に 引っ張り出され、一緒に躯体外観をチェックしたことがある。現場で最初に目に付くのが、 戸境壁のひび割れで、一枚の壁に0.2 〜0.3mmのひび割れが3 〜4 本生じていた。これを見た 構造設計者は、とても驚いていた。彼は、工事中の躯体外観を見るのは初めてで、脱型直後の躯 体にひび割れが発生するとは思っていなかったのだ。 監理者が打ち上がった躯体に注意を払うことで、防止できるひび割れもある。例えば、 型枠のサポート材の早期撤去によるひび割れだ。脱型した型枠搬出のため、つい部分的に 型枠サポート材を外したり、一時的に外す「盛り替え」を行ってしまったりすることがある。 こうした個所には、鉛直方向に切れ味の鋭いひび割れが生じる。上階のコンクリート打設時に 衝撃荷重がかかるからだ。よく見かけるのが、戸境壁に近い小梁のサポート材を撤去してしまう例だ。 壁の型枠を撤去する際、邪魔になるので外してしまうのである。同様に、バルコニーの型枠を搬出す るために、開口部のサポート材を外した例も時折、見掛ける。型枠の搬出経路に当たる部分のサポート材 は要注意である。 |
|||||||||||
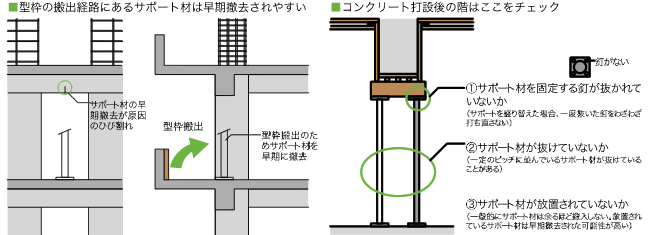 |
|||||||||||
|
|||||||||||
充てん性が良い修復材ひび割れの治療方法には、三つのタイプがある。(1)表面処理工法(2)注入工法 (3)充てん工法、である。筆者が協力している穂高工房は、微細な乾燥収縮などの ひび割れには微粒子高炉スラグ材による表面処理工法や注入工法を採用している。一般的には、U カットして樹脂系材料を充てんする「充てん工法」が普及している。 だが、乾燥収縮で起きるひび割れに、充てん工法で樹脂系材料を使うと、接着力があるため、 新たにひび割れを発生させる可能性があるし、修復跡が目立ってしまう。さらに、 ひび割れ部が乾いていないと接着しないことがある。 こうした知識を持つ人はまだまだ少数だ。微粒子高炉スラグ材がひび 割れの修復に適していることを確認した出来事を一つ紹介する。ある大手ゼネコンから、教育施設 のコンクリート躯体に発生したひび割れの修復依頼があった。ひび割れの幅は0.1 〜0.35mm程度。樹脂系材 料では完全な充てんが難しいと判断して、微粒子高炉スラグ材の使用を提案した。 |
|
||||||||||
|
現場所長は、エポキシ樹脂剤の注入しか経験がなかったが、高炉スラグ材に興味をもっていたので、採用
することになった。ところが、設計事務所からストップがかかった。監理の担当者は、微粒子高炉スラグ
材を使ったことがなく、経験的にエポキシ樹脂剤で注入できると主張する。そこで、樹脂注入を手がける専
門工事会社を現場に呼び、エポキシ樹脂剤と微粒子高炉スラグ材の充てん性能を比較することになった。 方法は、壁を貫通しているひび割れを対象にして、充てん状況を見るというものだ。充てんする壁の反対 側にひび割れから材が出ないようにシールを施す。その際、注入が確認できるようシールを一部、取り付け ずに透明なプラスチック板で押さえた。その結果、エポキシ樹脂剤は裏面まで届かなかったが、微粒子高炉 スラグ材は裏面まで到達したのを確認できた。さらに監理者は、壁に高圧水を掛けて、壁裏面への漏水を調 べるよう提案。エポキシ樹脂剤では数個所に漏水が見られたが、微粒子高炉スラグ材では漏水がなかった。 こうして微粒子高炉スラグ材の充てん性能の高さが確認され、監理者も納得して現場で採用できた。 ひび割れに関する一般の人々の意識は高まるばかりだ。建築の専門家も、よくよく知識を身に着けておか ないと、一般の人々を納得させる十分な説明やきちんとした修復ができない。その結果、信頼を失い、問題 を深刻にしかねない。ひび割れといえども軽視せず、真摯に取り組み、新しい材料や技術の習得に、共に努 めていきたい。 |
|||||||||||
 |
|||||||||||