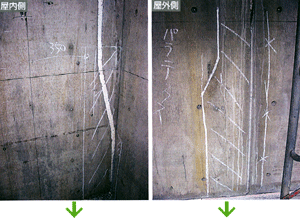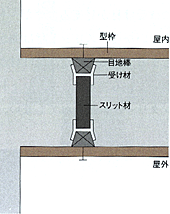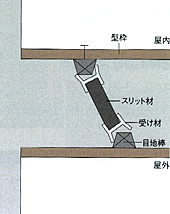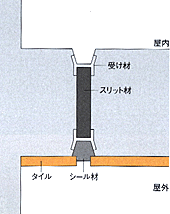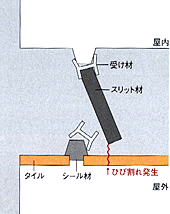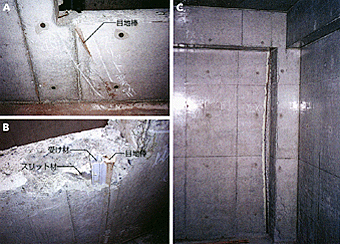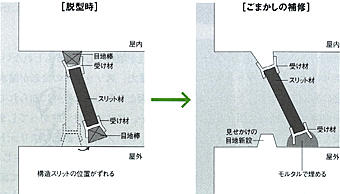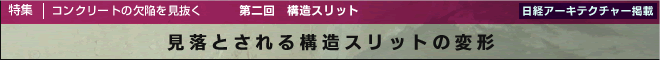
|
| 構造スリットは、打ち込んだコンクリートに押されて曲がってしまうことがある。脱型時に気付けば対処できるが、 意外に見落とされる。竣工後に、ひび割れや漏水などが発生し、原因調査の中で発覚することもしばしばだ。 現場での見つけ方や修復方法を解説する。 | |||||||||||||
 |
|||||||||||||
|
一枚の壁の裏表で構造スリット※1の見え方が違っているという不具合の修復を手がけた。
構造スリットは、配筋した後、型枠の組み立て完了間際に大工が取り付ける。その取り付け方が悪いと、
打設時に変形してしまい、本来の位置からずれてしまう。この現場では、屋外側の目地は真っすぐ見えるのに、
屋内側の目地は下の方が大きく柱側に曲がっていた。 構造スリットは、製品によって色々な取り付け方がある。スリット材※2を型枠の中にただ置いただけのようなタイプから、 金具でセパレーターなどにがっちり固定するタイプまで、様々だ。よく見かけるのは、目地棒に取り付けたプラスチック製 の受け材でスリット材を両端から挟み込むタイプだ。事例の現場でも、このタイプを使っていた。変形の原因は、 室内側の受け材を支える目地棒が型枠から外れたことだ。止め釘の打ち忘れやピッチが粗いためだ。 現場の職人は、ずれた目地棒の位置にシール材を施した。この結果、屋外側からは真っすぐ見えるのに、 屋内側では柱側に大きく曲がった、おかしな目地が出来上がった。この目地を見た建設会社の担当者が、 自社の技術担当者に相談して、筆者が修復を担当することになった。 この事例では、スリット材の変形がコンクリートの表面に表れていたので、現場の担当者にもすぐに発見できた。 むしろ問題は、コンクリートの中でスリット材が変形しているのに、目地は真っすぐに通っている場合だ。これは、 目地棒は型枠に固定されたまま、受け材が傾いてスリット材が変形した場合に発生する。 目地棒の位置は真っすぐなので、表面上はスリット材の変形を確認できないのである。 |
|
||||||||||||
放置される曲がったスリット材こんなエピソードがある。知り合いの構造設計者の案内で、ある現場を見学した。この時、 同行の穂高工房メンバーが次々とスリット材の変形を発見してしまった。構造監理者も施工者も、 壁の中で起こっているスリット材の変形には気付いていなかったのである。 このエピソードの現場に限らず、変形したスリット材がコンクリートの中に曲がった状態で放置 されている現場はたくさんあるのではないかと懸念している。スリット材が曲がると、構造設計者が想定しているような構造耐力が発揮されない恐れもある。 例えば、柱寄りに曲がったスリット材がフープ筋に密着してしまった場合、柱の断面が削られた断面欠損となる。 最も恐ろしいのは、構造スリットの設け忘れである。短柱としないため、柱と腰壁の間に入れるべき構造スリットを現場で設け忘れてしまうことがある。 これは、大地震発生時に柱が壊れてしまうかもしれない。 また、スリット材の変形が漏水の原因となることは意外に知られていない。スリット材が曲がってしまうと、 コンクリート表面にスリット材の位置の通りにひび割れが生じる。本来の位置には、目地を設けて漏水に対処しているが、 何の対策も施されていない位置にひび割れができれば、水は簡単に浸入してしまう。構造スリットの変形は、このようなリスクを伴うのである。 |
|
||||||||||||
目地棒の跡をよく見るスリット材の変形を見分ける方法の一つは、目地棒の跡をよく見ることだ。スリット材にプラスチックの受け材が付いたタイプなら、 溝の奥には受け材が見えるはずだ。もし見えないなら、スリット材は曲がってしまっている。また、受け材が横を向いている場合は、 スリット材がコンクリートに押されてしまい、曲がってしまった可能性が高い。もう一つの見分け方は、構造スリットのわきにひび割れが生じていないかを探すことだ。曲がったスリット材の位置に、 ひび割れが早くも施工中に生じてしまうことがあるのだ。 こうした注意信号を見逃さないように、注意深くコンクリートの表面を観察することが重要になる。 構造スリットの変形を防止するには、スリットを厳重に固定するとともに、スリットの位置ではコンクリートを慎重に打設する。 意識の高い現場では、スリットの位置にある鉄筋に赤い布などの目印を付けて、現場作業員の注意を喚起している。 曲がってしまった構造スリットに、ごまかしの補修を施した現場を見かけたことがある。本来の目地位置に見せかけの目地を掘り、 ずれた目地棒の跡をモルタルで埋めてしまうのだ。これでは、構造スリット本来の役割を果たさず、漏水を引き起こすことになる。 われわれは、変形したスリット材を完全に撤去して、本来の設置位置に構造スリットを据え直す。設計図の性能に戻す「修復」を、 モットーとしているのである。 |
|
||||||||||||
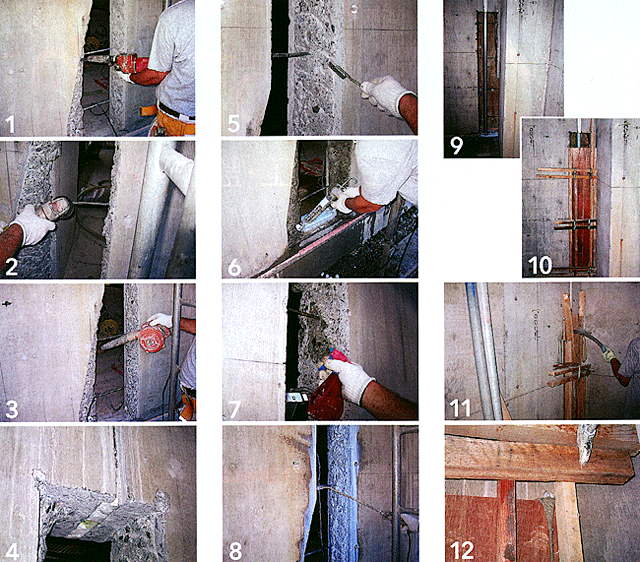 |
|||||||||||||
|
[修復の手順] 1 変形した構造スリットの周辺のコンクリートをはつり、その面に残る浮いた材をタガネ で落とす 2 鉄筋をワイヤブラシで清掃 3 はつり面に残るホコリをブロアーで落とす 4 はつった個所 の上端部に空気抜きの穴を設ける 5 はつった面をワイヤブラシで清掃 6 壁の下端に水平スリットがある場合は、スリット材の上から防潤ゴムでシールをする 7 鉄筋に防錆剤を塗布 8 コンクリートのはつり面に吸水防止剤を散布 9 構造スリットを設置 10 型枠を設置 11 無収縮コンクリートを打設。その後、上端部のみ無収縮モルタルを圧入 12 空気抜き穴から無収縮モルタルが漏れるのを確認して打設完了 |
|||||||||||||
構造スリットに頼らぬ設計を「構造スリットを使うと構造設計は楽になる」という話を現場で耳にする。だが、 スリット材が曲がると、建物の構造安全性が確保できず、漏水の原因にもなる。設計者は、 こうしたリスクがあることを理解して、極力、構造スリットに頼らない設計を心がけてほしい。 雨がかりとなる外壁面にはできるだけ構造スリットを用いないような設計ができれば、漏水のリスクは大きく減らせる。今、構造計算書の偽造が社会問題となっていて、構造設計者のモラルが問われている。構造設計者・監理者は、 躯体施工中に構造スリットの施工状態を確認してはどうだろうか。建築はしょせん、職人の手でつくられている。 リスクを回避するためにも、施工ミスが生じやすい納まりを極力避けるよう知恵を絞ることも設計者の仕事ではないだろうか。 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||